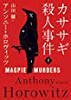 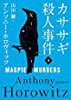 |
「カササギ殺人事件(上) ★★★★☆ アンソニー・ホロヴィッツ 東京創元社 2018.12.6 記 |
| 元々大作は好きだし、作中作自体も読み応えがある入れ子構造となった本書は、私のような向きにとっては贅沢とかゴージャスとかいった形容がふさわしい小説かもしれない。 随所で言及もされているが、コナン・ドイルやアガサ・クリスティなどのいわゆる英国古典ミステリーを彷彿させる空気にも満ちていて、嬉しくなる。 「絹の家」を物している著者だから当然ではあるけれど。 発見された作中作の最終章で、ピュント氏が推論のみをベースにしながら、ズドンと断じきるところも、いかにも、”らしい”(笑)。 途中で正直、中だるみするところもあるので、ヴォリュームはもう少し絞り込めたとは思うし、本編・作中作ともに物語の仕舞い方が若干乱暴だなとも感じるが、上質のエンターテインメントであることは間違いない。 |
|